黒澤監督を支えた世界の名映画撮影技師、宮川一夫
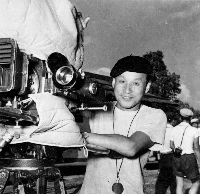 先ごろ、91歳の高齢で亡くなった宮川一夫は、映画監督として世界の「クロサワ」と呼ばれる黒澤明と同じで、映画撮影技師として世界の「ミヤガワ」と称された、偉大な映画カメラマンです。彼の作風は、溝口健二や黒澤明などの名監督の作品において大きな役割をはたしました。宮川のカメラワークなしには、溝口も黒澤も世界の映画コンクールで数々の栄誉には輝かなかったと言っても過言ではありません。今回は、この宮川一夫の撮影テクニックと映画において表現された宮川芸術を紹介します。
先ごろ、91歳の高齢で亡くなった宮川一夫は、映画監督として世界の「クロサワ」と呼ばれる黒澤明と同じで、映画撮影技師として世界の「ミヤガワ」と称された、偉大な映画カメラマンです。彼の作風は、溝口健二や黒澤明などの名監督の作品において大きな役割をはたしました。宮川のカメラワークなしには、溝口も黒澤も世界の映画コンクールで数々の栄誉には輝かなかったと言っても過言ではありません。今回は、この宮川一夫の撮影テクニックと映画において表現された宮川芸術を紹介します。
カメラマンの丁稚奉公
1908年生まれの宮川は、昭和元年に、ふとしたことがきっかけで映画の世界に足を踏み入れました。当時、スチルカメラに興味を持っていた宮川青年は、友人が日活撮影所にいた関係で、しばしば彼にフィルムの現像を頼みました。その見返りとして日活野球部の助っ人をしているうちに、撮影所の仕事を手伝うようになりました。現在のようにカメラマンの専門学校があるわけではありませんから、3年間の現像処理の仕事に続き、その後12年間の撮影助手、例えば、カメラのピントのみを手動で合わせるピントマンを経験し、晴れて撮影技師になることができました。この時の15年間の修行が宮川にとって、撮影テクニックの基本を習得する場であったと後に述べています。サイレント時代からカメラマンをしていた宮川の作品の多くは、白黒です。彼は映画作品だけで、136の作品にカメラマンとして関わりましたが、その半分以上がモノクロ作品でした。しかし、その単色の作品で最も色を感じさせることのできる色調を出せたのは、世界において宮川カメラマンをおいて他にいません。
日本の水墨画を感じさせるカメラワーク
宮川が撮影でこだわったのは、鼠(ねずみ)色です。白黒映画は単純に言えば、白と黒の2階調ですが、鼠色には無限の色があるというのが彼の持論でした。宮川に日本画を教えた先生が、彼に絵の具を一切使わせなかったため、彼は鼠色の中で自然の色を表現しようと努力しました。その教えが後のカメラワークに多大な影響を与えています。白黒映画は、その色の階調から光と影の表現が重要でした。従って、光と影のコントラスト、その中間に位置する鼠色の表現方法により、作品の雰囲気が大幅に変わりました。カラー時代のカメラワークが、動きやカットの仕方に重きを置いているのと比べて、白黒時代は、光と影のコントラストをどう表現するかにより、硬調か軟調かの絵作りを監督や脚本家も含めて、論じられました。そのためか、カメラマンの技量や美的センスがより作品に反映されたのも事実です。宮川はモノトーンで自分が育った京都の色彩を出していたと言っています。
「羅生門」で見せたカメラワークの芸術
 1950年の作品、「羅生門」は黒澤監督にとっても、宮川にとっても、ターニングポイントとなった作品です。もともと軟調指向の宮川のカメラワークは、ダイナミックな絵作りを目指す黒澤とは相容れない部分がありました。監督から「太陽を画調としてどう考えるか?」という難題を投げかけられて、宮川が答えたのは、「白と黒と鼠、この3つの色でこの映画を撮りたい」というものでした。監督は了解し、最初の難題が、「羅生門」の話の中で、主役となる盗賊と暴行を受ける侍の妻との抱擁シーンでした。2人のバックに太陽が背景に映っているコントラストの強いカットを望んだのです。しかし、一般に太陽を大きく撮るには望遠レンズが必要ですし、通常、人物を撮るのは標準レンズです。ズームカメラなどない時代ですから、ほとんど手作りの手法を編み出すしかありません。そこで考えられたのが、25メートルの高さのやぐらの上で三船敏郎と京マチ子の2人に演技してもらい、それを下から太陽を背に撮りながら絞りを最小にして、2人と太陽をくっきりと撮影しました。何のことはない原始的な方法ですが、必要に応じて様々な撮影方法を試しました。批評家から絶賛された薮(森)のなかのシーン。例えば、三船が延々と薮の中を走りまくるシーン、森の中の木洩れ日や風にゆれる木の葉の影など、海外のカメラマンを驚嘆させました。タネを明かせば、延々と走っているのは同じところで、カットにより走り続けるように見せたのです。三船が走る前に現れる木の葉は、撮影助手がレンズの前に枝を置いたもの、森の中での影の絞り込みは、鏡に光を反射させて陰影を表現したもの、すべて宮川のスタッフが手作りで表現した特殊効果など一切ない世界です。このような絶え間ない努力と工夫が、黒澤の作品を色彩感が強いダイナミックな作品に仕上げました。そして結果が、翌年のベネチアの映画祭におけるグランプリ受賞です。
1950年の作品、「羅生門」は黒澤監督にとっても、宮川にとっても、ターニングポイントとなった作品です。もともと軟調指向の宮川のカメラワークは、ダイナミックな絵作りを目指す黒澤とは相容れない部分がありました。監督から「太陽を画調としてどう考えるか?」という難題を投げかけられて、宮川が答えたのは、「白と黒と鼠、この3つの色でこの映画を撮りたい」というものでした。監督は了解し、最初の難題が、「羅生門」の話の中で、主役となる盗賊と暴行を受ける侍の妻との抱擁シーンでした。2人のバックに太陽が背景に映っているコントラストの強いカットを望んだのです。しかし、一般に太陽を大きく撮るには望遠レンズが必要ですし、通常、人物を撮るのは標準レンズです。ズームカメラなどない時代ですから、ほとんど手作りの手法を編み出すしかありません。そこで考えられたのが、25メートルの高さのやぐらの上で三船敏郎と京マチ子の2人に演技してもらい、それを下から太陽を背に撮りながら絞りを最小にして、2人と太陽をくっきりと撮影しました。何のことはない原始的な方法ですが、必要に応じて様々な撮影方法を試しました。批評家から絶賛された薮(森)のなかのシーン。例えば、三船が延々と薮の中を走りまくるシーン、森の中の木洩れ日や風にゆれる木の葉の影など、海外のカメラマンを驚嘆させました。タネを明かせば、延々と走っているのは同じところで、カットにより走り続けるように見せたのです。三船が走る前に現れる木の葉は、撮影助手がレンズの前に枝を置いたもの、森の中での影の絞り込みは、鏡に光を反射させて陰影を表現したもの、すべて宮川のスタッフが手作りで表現した特殊効果など一切ない世界です。このような絶え間ない努力と工夫が、黒澤の作品を色彩感が強いダイナミックな作品に仕上げました。そして結果が、翌年のベネチアの映画祭におけるグランプリ受賞です。
フィルム1コマの集中
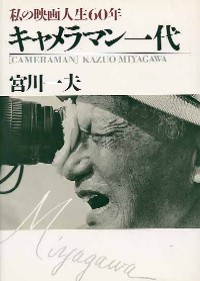 宮川が後輩のカメラマンに残した言葉で、意味深いものがあります。要約しますと「映画の1コマに集中する情熱。例えば、茶碗一つ取るにしても、そこに暖かな雰囲気をだす細かな神経が必要である。脚本を読んで、それが熱いお茶か冷たいお茶かをきちんと描くことが大事である」さらにこう続けています。「手作りで1コマ1コマ描くというと、時間がかかってしょうがないと言うが、それは違う。カメラを構えて、1コマにいかにスタッフの思いを注ぐか、時間がかかるものではない。そういう見極め方や、内容の把握の仕方がとても大切なのです」確かになにを創るにも、作者の思いがなければ、たとえ技巧的に優れていても、結果はつまらないものになりがちです。物の見極め方や内容を把握する力は、実は普段からの旺盛な好奇心や学習から得られるもので、長い時間をかけて身につくものです。勉強家で芸術に造詣が深かった宮川だからこそ、あの独特で美しい映像が表現し得たと言えるでしょう。そういう意味でも、宮川一夫は世界的に傑出したカメラマンでした。(nao)
宮川が後輩のカメラマンに残した言葉で、意味深いものがあります。要約しますと「映画の1コマに集中する情熱。例えば、茶碗一つ取るにしても、そこに暖かな雰囲気をだす細かな神経が必要である。脚本を読んで、それが熱いお茶か冷たいお茶かをきちんと描くことが大事である」さらにこう続けています。「手作りで1コマ1コマ描くというと、時間がかかってしょうがないと言うが、それは違う。カメラを構えて、1コマにいかにスタッフの思いを注ぐか、時間がかかるものではない。そういう見極め方や、内容の把握の仕方がとても大切なのです」確かになにを創るにも、作者の思いがなければ、たとえ技巧的に優れていても、結果はつまらないものになりがちです。物の見極め方や内容を把握する力は、実は普段からの旺盛な好奇心や学習から得られるもので、長い時間をかけて身につくものです。勉強家で芸術に造詣が深かった宮川だからこそ、あの独特で美しい映像が表現し得たと言えるでしょう。そういう意味でも、宮川一夫は世界的に傑出したカメラマンでした。(nao)
宮川一夫の略歴
本名宮川一雄 1908年(明治41年)2月25日、京都市生まれ。京都商卒業後、18歳で日活京都へ現像部助手として入社する。撮影技師(カメラマン)昇進第1作は「お千代傘」(尾崎純監督)。43年(昭和18年)の「無法松の一生」(稲垣浩監督)の美しい映像で高い評価を得て、溝口健二、黒沢明、小津安二郎、市川崑監督ら巨匠の作品を撮影し始める。黒沢監督との初コンビ「羅生門」(50年)は、日本映画史上初の国際賞となるベネチア国際映画祭金獅子(きんじし)賞を受賞。「雨月物語」(溝口監督)は英国エジンバラ芸術祭で最高賞受賞。「用心棒」(黒沢監督)などでNHK映画賞撮影賞。「おとうと」「はなれ瞽女(ごぜ)おりん」「瀬戸内少年野球団」などで毎日映画コンクール撮影賞など、受賞多数。78年に紫綬褒章、83年に勲4等旭日小綬章。92年(平成4年)には山路ふみ子文化賞、川喜多賞を受賞。映画134本、テレビ映画8本を撮影。宮川最後の作品は篠田正浩監督の「舞姫」(89年)。

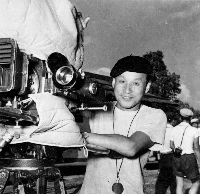 先ごろ、91歳の高齢で亡くなった宮川一夫は、映画監督として世界の「クロサワ」と呼ばれる黒澤明と同じで、映画撮影技師として世界の「ミヤガワ」と称された、偉大な映画カメラマンです。彼の作風は、溝口健二や黒澤明などの名監督の作品において大きな役割をはたしました。宮川のカメラワークなしには、溝口も黒澤も世界の映画コンクールで数々の栄誉には輝かなかったと言っても過言ではありません。今回は、この宮川一夫の撮影テクニックと映画において表現された宮川芸術を紹介します。
先ごろ、91歳の高齢で亡くなった宮川一夫は、映画監督として世界の「クロサワ」と呼ばれる黒澤明と同じで、映画撮影技師として世界の「ミヤガワ」と称された、偉大な映画カメラマンです。彼の作風は、溝口健二や黒澤明などの名監督の作品において大きな役割をはたしました。宮川のカメラワークなしには、溝口も黒澤も世界の映画コンクールで数々の栄誉には輝かなかったと言っても過言ではありません。今回は、この宮川一夫の撮影テクニックと映画において表現された宮川芸術を紹介します。
 1950年の作品、「羅生門」は黒澤監督にとっても、宮川にとっても、ターニングポイントとなった作品です。もともと軟調指向の宮川のカメラワークは、ダイナミックな絵作りを目指す黒澤とは相容れない部分がありました。監督から「太陽を画調としてどう考えるか?」という難題を投げかけられて、宮川が答えたのは、「白と黒と鼠、この3つの色でこの映画を撮りたい」というものでした。監督は了解し、最初の難題が、「羅生門」の話の中で、主役となる盗賊と暴行を受ける侍の妻との抱擁シーンでした。2人のバックに太陽が背景に映っているコントラストの強いカットを望んだのです。しかし、一般に太陽を大きく撮るには望遠レンズが必要ですし、通常、人物を撮るのは標準レンズです。ズームカメラなどない時代ですから、ほとんど手作りの手法を編み出すしかありません。そこで考えられたのが、25メートルの高さのやぐらの上で三船敏郎と京マチ子の2人に演技してもらい、それを下から太陽を背に撮りながら絞りを最小にして、2人と太陽をくっきりと撮影しました。何のことはない原始的な方法ですが、必要に応じて様々な撮影方法を試しました。批評家から絶賛された薮(森)のなかのシーン。例えば、三船が延々と薮の中を走りまくるシーン、森の中の木洩れ日や風にゆれる木の葉の影など、海外のカメラマンを驚嘆させました。タネを明かせば、延々と走っているのは同じところで、カットにより走り続けるように見せたのです。三船が走る前に現れる木の葉は、撮影助手がレンズの前に枝を置いたもの、森の中での影の絞り込みは、鏡に光を反射させて陰影を表現したもの、すべて宮川のスタッフが手作りで表現した特殊効果など一切ない世界です。このような絶え間ない努力と工夫が、黒澤の作品を色彩感が強いダイナミックな作品に仕上げました。そして結果が、翌年のベネチアの映画祭におけるグランプリ受賞です。
1950年の作品、「羅生門」は黒澤監督にとっても、宮川にとっても、ターニングポイントとなった作品です。もともと軟調指向の宮川のカメラワークは、ダイナミックな絵作りを目指す黒澤とは相容れない部分がありました。監督から「太陽を画調としてどう考えるか?」という難題を投げかけられて、宮川が答えたのは、「白と黒と鼠、この3つの色でこの映画を撮りたい」というものでした。監督は了解し、最初の難題が、「羅生門」の話の中で、主役となる盗賊と暴行を受ける侍の妻との抱擁シーンでした。2人のバックに太陽が背景に映っているコントラストの強いカットを望んだのです。しかし、一般に太陽を大きく撮るには望遠レンズが必要ですし、通常、人物を撮るのは標準レンズです。ズームカメラなどない時代ですから、ほとんど手作りの手法を編み出すしかありません。そこで考えられたのが、25メートルの高さのやぐらの上で三船敏郎と京マチ子の2人に演技してもらい、それを下から太陽を背に撮りながら絞りを最小にして、2人と太陽をくっきりと撮影しました。何のことはない原始的な方法ですが、必要に応じて様々な撮影方法を試しました。批評家から絶賛された薮(森)のなかのシーン。例えば、三船が延々と薮の中を走りまくるシーン、森の中の木洩れ日や風にゆれる木の葉の影など、海外のカメラマンを驚嘆させました。タネを明かせば、延々と走っているのは同じところで、カットにより走り続けるように見せたのです。三船が走る前に現れる木の葉は、撮影助手がレンズの前に枝を置いたもの、森の中での影の絞り込みは、鏡に光を反射させて陰影を表現したもの、すべて宮川のスタッフが手作りで表現した特殊効果など一切ない世界です。このような絶え間ない努力と工夫が、黒澤の作品を色彩感が強いダイナミックな作品に仕上げました。そして結果が、翌年のベネチアの映画祭におけるグランプリ受賞です。
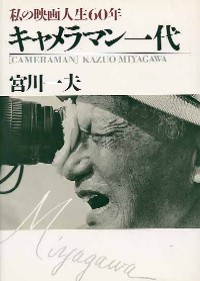 宮川が後輩のカメラマンに残した言葉で、意味深いものがあります。要約しますと「映画の1コマに集中する情熱。例えば、茶碗一つ取るにしても、そこに暖かな雰囲気をだす細かな神経が必要である。脚本を読んで、それが熱いお茶か冷たいお茶かをきちんと描くことが大事である」さらにこう続けています。「手作りで1コマ1コマ描くというと、時間がかかってしょうがないと言うが、それは違う。カメラを構えて、1コマにいかにスタッフの思いを注ぐか、時間がかかるものではない。そういう見極め方や、内容の把握の仕方がとても大切なのです」確かになにを創るにも、作者の思いがなければ、たとえ技巧的に優れていても、結果はつまらないものになりがちです。物の見極め方や内容を把握する力は、実は普段からの旺盛な好奇心や学習から得られるもので、長い時間をかけて身につくものです。勉強家で芸術に造詣が深かった宮川だからこそ、あの独特で美しい映像が表現し得たと言えるでしょう。そういう意味でも、宮川一夫は世界的に傑出したカメラマンでした。(nao)
宮川が後輩のカメラマンに残した言葉で、意味深いものがあります。要約しますと「映画の1コマに集中する情熱。例えば、茶碗一つ取るにしても、そこに暖かな雰囲気をだす細かな神経が必要である。脚本を読んで、それが熱いお茶か冷たいお茶かをきちんと描くことが大事である」さらにこう続けています。「手作りで1コマ1コマ描くというと、時間がかかってしょうがないと言うが、それは違う。カメラを構えて、1コマにいかにスタッフの思いを注ぐか、時間がかかるものではない。そういう見極め方や、内容の把握の仕方がとても大切なのです」確かになにを創るにも、作者の思いがなければ、たとえ技巧的に優れていても、結果はつまらないものになりがちです。物の見極め方や内容を把握する力は、実は普段からの旺盛な好奇心や学習から得られるもので、長い時間をかけて身につくものです。勉強家で芸術に造詣が深かった宮川だからこそ、あの独特で美しい映像が表現し得たと言えるでしょう。そういう意味でも、宮川一夫は世界的に傑出したカメラマンでした。(nao)