

音楽一家ヴィスコンティ
ルキノの母カルラは大のオペラファンで、母方の祖父ルイジはオペラ大作曲家ヴェルディの親友であり、本人も作曲家でした。また父の兄ウベルトはミラノスカラ座の経営を引き受け、多くの資金を注ぎ込みました。このときスカラ座の音楽監督には名指揮者トスカニーニを招き、スカラ座黄金時代を築きます。ヴィスコンティ家はそのような関係もあり、ルキノの子供の頃は、日曜の午後はスカラ座の4号桟敷席(ヴィスコンティ家専用)でオペラなどを観賞するのが習わしとなっていました。ルキノ自身もチェロが得意で、演奏家として出演するほどの腕を持ち、音楽は最も好きな学科でした。
第一次大戦が始まった頃、父のジョゼッペはミラノ芸術演劇座を興行します。これがきっかけとなり徐々ではありますが、ルキノは舞台の世界にのめり込んでいきます。ヴィスコンティは当然ながら、数々の素晴らしい映画で知られていますが(と言っても生涯19本作品を撮っただけです)、彼が映画の世界に入ったのはまったくの偶然の出来事からでした。21歳の時、自動車事故を起こして、隣に座らせた運転手を死なせてしまったルキノは、精神的な痛手を癒すため、放浪の旅に出ました。彼ははじめ、北アフリカのサハラ砂漠を旅し、一時帰国した後にはロンドン、パリに渡り、ジャン・コクトー、ブレヒト、ココ・シャネルなど当時の文化人と交流しました。特にパリでは、映画に魅せられ、帰国後自ら16ミリカメラを購入し、映画づくりを始めます。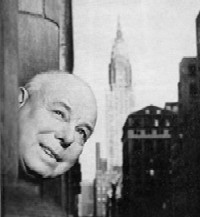
監督ジャン・ルノワールとの出会い
そんな折り、ロンドンで初の映画の仕事を受けられるとの話しがあり、プロデューサーを訪ねて行きますが、結局実らず、失意のなかパリに立ち寄ります。ルキノの話を聞いた旧知のシャネルはいたく同情し、後にフランスの大監督となったジャン・ルノワールを紹介します。ルキノが30歳の夏です。彼はルノワール監督の「ピクニック」の第3助手として採用されてから、「どん底」や「大いなる幻影」も少し手伝いました。彼の映画人としてのスタートはここからです。
映画界に入って6年後、ルノワールに勧められていた「郵便配達は2度ベルを鳴らす」を映画化して(1942年)、センセーショナルな反響を呼んだ後、彼は反ファシストのレジスタンス活動に身を投じて、しばらく映画界から遠ざかります。レジスタンス活動で九死に一生を得た後、彼は演劇に戻り、コクトー作の「恐るべき親たち」で大成功を収めます。演劇界では新人にすぎないヴィスコンティは、従来の過剰演出から徹底的なリアリズムに即した演出でイタリア演劇界に一石を投じます。それからしばらく演劇に没頭して、'47年のネオ・リアリズムの傑作映画「揺れる大地」を発表するまで、演劇界で揺るぎない地位を確立します。
マリア・カラスとの出会い
 イタリアでのヴィスコンティの名声は映画監督と言うより、数々の既成のスタイルを打ち破った演劇/オペラの先駆的な演出家として高いようです。特に1940年後半から50年代はイタリアで初演したアーサー・ミラー作「セールスマンの死」、テネシー・ウィリアムズ作「欲望という名の電車」など名作舞台の他、「フィガロの結婚」「椿姫」「サロメ」などのオペラの演出で活躍します。特に、マリア・カラスとの出会いはイタリアオペラ界の黄金期を作り上げました。1954年12月、スカラ座の「ラ・ヴェスターレ」で初めてマリア・カラスの演出を行い、そして翌年には、ベリーニの「夢遊病の女」、ヴェルディの「椿姫」を演出します。デビュー間もないカラスは素晴らしい歌手であっても、まだ、舞台での演技は完成されていませんでした。しかしヴィスコンティの緻密な演出と徹底した演技指導で、カラスは演技にも開眼。その後一気にスターダムにのしあがっていきます。このとき指導されたマドンナ役はその後もカラスの当たり役となっています。ヴィスコンティの偉大さはその優れた演技指導で舞台上の役者の能力を最大限に引き出すだけでなく、演出解釈の上でも数々の功績を生んでいます。彼の舞台上の演出の本質は、台本の正確な解釈、そしてそれに対する役者の忠実な演技です。この手法は映画演出の際にも取り入れて、各シークエンスごとの撮影前に舞台と同様な長時間リハーサルを行い、本番撮影に入ったというエピソードも残っています。
イタリアでのヴィスコンティの名声は映画監督と言うより、数々の既成のスタイルを打ち破った演劇/オペラの先駆的な演出家として高いようです。特に1940年後半から50年代はイタリアで初演したアーサー・ミラー作「セールスマンの死」、テネシー・ウィリアムズ作「欲望という名の電車」など名作舞台の他、「フィガロの結婚」「椿姫」「サロメ」などのオペラの演出で活躍します。特に、マリア・カラスとの出会いはイタリアオペラ界の黄金期を作り上げました。1954年12月、スカラ座の「ラ・ヴェスターレ」で初めてマリア・カラスの演出を行い、そして翌年には、ベリーニの「夢遊病の女」、ヴェルディの「椿姫」を演出します。デビュー間もないカラスは素晴らしい歌手であっても、まだ、舞台での演技は完成されていませんでした。しかしヴィスコンティの緻密な演出と徹底した演技指導で、カラスは演技にも開眼。その後一気にスターダムにのしあがっていきます。このとき指導されたマドンナ役はその後もカラスの当たり役となっています。ヴィスコンティの偉大さはその優れた演技指導で舞台上の役者の能力を最大限に引き出すだけでなく、演出解釈の上でも数々の功績を生んでいます。彼の舞台上の演出の本質は、台本の正確な解釈、そしてそれに対する役者の忠実な演技です。この手法は映画演出の際にも取り入れて、各シークエンスごとの撮影前に舞台と同様な長時間リハーサルを行い、本番撮影に入ったというエピソードも残っています。
「ルードウィヒ神々の黄昏」
 ヴィスコンティの作品の中で、1973年作の「ルードウィヒ神々の黄昏」も彼とオペラの強い結びつきが感じられるものです。「ベニスに死す」に続くドイツもののこの第3作目は、ワグナーを庇護したバイエルン国王ルードウィヒ2世を題材にし、ワグナーの作品が華麗に使われています。意外ですが、ヴィスコンティ自身は1度もワグナー作品を舞台で演出したことはなく、最も愛したオペラ作曲家はヴェルディでした。彼はこの作品の編集中に発作で倒れ、生死をさまよいますが、完成への執念で奇跡的に回復します。ヴィスコンティは主人公の国王と同様に、この作品の完成には狂気的でさえありました。また、ルードウィヒと同じく一生独身で過ごしました。
(nao)
ヴィスコンティの作品の中で、1973年作の「ルードウィヒ神々の黄昏」も彼とオペラの強い結びつきが感じられるものです。「ベニスに死す」に続くドイツもののこの第3作目は、ワグナーを庇護したバイエルン国王ルードウィヒ2世を題材にし、ワグナーの作品が華麗に使われています。意外ですが、ヴィスコンティ自身は1度もワグナー作品を舞台で演出したことはなく、最も愛したオペラ作曲家はヴェルディでした。彼はこの作品の編集中に発作で倒れ、生死をさまよいますが、完成への執念で奇跡的に回復します。ヴィスコンティは主人公の国王と同様に、この作品の完成には狂気的でさえありました。また、ルードウィヒと同じく一生独身で過ごしました。
(nao)